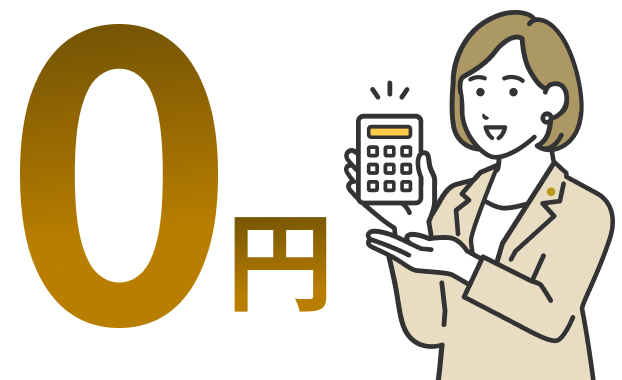遺言書の財産目録とは? 作成するメリットや注意点を弁護士が解説
- 遺言
- 遺言書
- 財産目録
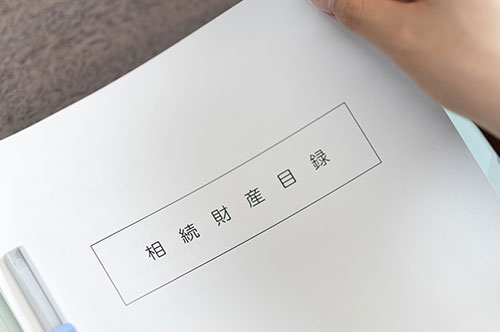
令和4年9月に法務省が公表したアンケート結果によれば、相続人になったものの遺産分割をしなかった方の割合は36.0%、そのうち遺言書があったことから遺産分割の必要がなかった方の割合は13.4%でした。
このアンケートは、相続登記の義務化が始まることを受けて実施されたものです。その背景には、相続された土地や家屋がそのまま放置される問題が深刻化していることがあり、福山市でも、平成30年の時点で約1万3000戸の放置空き家が確認されています。
遺言書を残して、相続人の負担を軽くしたいけれども、何から手をつければいいのか分からない方もおられるかもしれませんが、まずはご自身の財産を把握する「財産目録」の作成から始めることをおすすめします。
今回のコラムでは、遺言書を残す場合にまず取りかかりたい財産目録の作成方法などについて、ベリーベスト法律事務所 福山オフィスの弁護士が解説します。


1、遺言書の財産目録とは?
遺言書の財産目録は、遺言を残す方が亡くなったときに相続の対象となる財産を一覧表にした書類です。なぜ財産や債務を一覧化した書類を作成したほうがいいのか、どのように作成すればいいのかについて解説します。
-
(1)財産目録を作成したほうがいい理由
財産目録は、遺言書の一部として使用するほかに、遺言以外の相続対策を検討する際にも有用な資料となります。
遺言書は、誰にどの財産を取得させるかを記載するのが主な目的なので、遺言の本文で財産の内容を記載してしまえば、財産目録は必ずしも添付する必要はありません。
しかし、財産目録があれば、相続財産の全容を一目で確認することができ、遺言書の本文も、以下のように簡潔に記載することができます。
「財産目録番号1の預貯金は妻○○に相続させる。」
「財産目録番号2及び3の不動産は長男△△に相続させる。」
また、遺言以外にも相続対策をお考えの場合も、まずご自身の財産や負債の状況について把握することが必要になりますが、財産目録を作成していると弁護士に相談する際にも大変有用です。 -
(2)財産目録はパソコンなどで作成できる
遺言書の一般的な作成方法は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。
- 自筆証書遺言とは
遺言者が全文を自筆で作成する方式ですが、財産目録の部分に限って自筆ではなくパソコンのワープロソフトなどで作成することが可能です。 - 公正証書遺言とは
公証人に遺言の内容を口頭で伝えて、公正証書の形式で遺言書を作成してもらう方式です。
公正証書遺言を作成する場合にも、どのような財産を保有しているのかを説明する資料として財産目録を使用します。
遺言を作成した後で財産の内容が変わったり、遺言の内容を変更したりする場合でも、財産目録をパソコンで作成しておけば、遺言書を書き換える労力も少なくなります。
- 自筆証書遺言とは
2、遺言書の財産目録を作成するメリット
遺言書に添付する財産目録を作成することは、遺言を残す方と財産を受け取る方の双方にとってメリットがあります。以下そのメリットについて解説します。
-
(1)遺言を残す方のメリット
財産目録の作成は、誰にどの財産を取得させるのかを検討するのが主な目的ですが、相続対策を検討するきっかけになることもあります。生前にできる相続対策の例を解説します。
- ① 相続税対策
贈与税が課税されない範囲で子や孫などに贈与をするなどして、早めに財産を移転して相続税が節税できる可能性があります。相続税対策は、できれば5年以上の期間をかけて行うことで、より効果が期待できるので、早めに準備をすることをおすすめします。 - ② 相続人の負担を軽減するための財産整理
相続人など親族が使用する見込みがない不動産がある場合は、早めに売却して現金化しておくことも有効です。不動産のまま相続すると管理費や固定資産税のコストがかかるため、そうした負担を軽減させるために早めの処分も検討してみましょう。 - ③ 家族の生活資金や納税資金を用意
不動産など換金しにくい財産が多い場合は、残された家族の生活資金や相続税の納税資金の手当てとして、生命保険契約を締結しておくことも選択肢となります。
- ① 相続税対策
-
(2)財産を受け取る方のメリット
遺言書がない場合の相続手続は以下のような手順で行います。
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 遺産分割協議
- 相続財産の名義変更手続
- 相続税の申告、納付
財産目録や遺言書がある場合に、相続手続の負担がどのように軽減されるのか解説します。
- ① 相続財産の調査が不要になる
遺言書や財産目録がない場合は、相続人が残された書類などを手掛かりにして財産や借金などの債務をすべて調査する必要があります。
相続財産の調査を行う期間は、借金の負担を相続人が負わずにすむ相続放棄の判断にも必要なため3か月が目安となります。しかし遺品の整理などを行いながら相続財産を調査するのはかなりの労力が必要です。
また、相続財産を隠しているのではないかなどと相続人同士で疑心暗鬼になってトラブルの原因となるケースもありますが、財産目録があればそのようなトラブルも避けることができます。 - ② 遺言書がある場合は遺産分割協議が不要になる
遺言書がない場合は、相続人全員で誰が何を相続するのかを話し合う遺産分割協議を行います。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の手続で遺産分割を行うことになりますが、解決まで1年以上を要することもあります。
相続財産の調査と遺産分割協議は、相続人にとって特に負担になる手続ですが、遺言書があればこれらの手続が不要になるのは大きなメリットといえます。 - ③ 相続税申告の要否が早期に判断できる
相続税は、すべての相続財産の評価額により課税の有無や税額が決まります。
また、相続税は法定相続人の人数によって基礎控除額が決まるため、相続財産の評価額が基礎控除額に収まるか否かは、相続人にとっても大きな関心事となります。
相続税の申告、納税は、相続手続の開始から10か月以内に行う必要があるので、遺言書や財産目録により相続財産がリスト化されていると、評価額の算定も格段に楽になります。
3、遺言書の財産目録を作る方法
財産目録の様式は特に決まりはありませんが、裁判所のウェブサイトなどの書式例を参考にすることもできます。
主な財産の記載例を紹介します。
① 預貯金・現金
預貯金は銀行名と支店、口座の種類、口座番号(記号・番号)により特定します。預貯金の残高は、財産目録の作成後に増減する可能性があるため、記載しないほうがよいでしょう。
預貯金を分割して遺贈する場合は、遺言の本文で「番号1の預貯金のうち、200万円は孫○○に相続させ、その余は妻△ △に遺贈する。」などと記載します。
- 1 ○○銀行△△支店 普通預金 口座番号1234567
- 2 現金 300万円 保管場所 ○○銀行△ △支店貸金庫
② 不動産
不動産は登記事項証明書の表題部に記載されている、所在、地番、地目、面積(建物は所在、家屋番号、種類、構造、床面積)をそのまま記載します。
未登記の不動産がある場合は、固定資産納税通知書に記載されている事項を参考にして記載するといいでしょう。また未登記の不動産は、相続に備えて保存登記しておくことをおすすめします。
- 1 建物(未登記につき現況)
所在 福山市○○町1番10号
家屋番号 未登記
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 60.55平方メートル
2階 45.00平方メートル
③ 有価証券等
株式や投資信託、国債や社債などは、残高証明書などを参照して、記載例のように資産を特定する事項を記載します。
- 1 上場株式
口座開設者 住所 広島県福山市□□□町N丁目N番地N号
(加入者) 氏名 ○○○○
口座番号 △△証券株式会社××支店NNNNN
銘柄 ○○物産株式会社普通株式
コード番号 NNNN
数量 500株 - 2 投資信託
口座開設者 住所 広島県福山市□□□町N丁目N番地N号
(加入者) 氏名 ○○○○
口座番号 △△信託銀行××支店NNNNN
銘柄 ○○ファンド
数量 100口
④ 生命保険等
遺言者が保険金受取人になっている生命保険は相続税の課税対象となり、遺言者が被保険者になっている生命保険は、契約者によって相続税、贈与税または所得税の課税対象となります。
保険証券に記載されている以下の事項を記載します。
- 1 生命保険
保険会社 ○○生命株式会社
保険証券番号 123456
契約者 遺言者△△
受取人 遺言者△△
⑤ 借金等の債務
借金などの債務も相続の対象になるので、相続人にとっては重要な情報になります。
他人の連帯保証人になっているものも記載します。
- 1 借入金(住宅ローン)
債権者 ○○銀行△△支店
契約日 令和○年○月○日
借入元本 200万円
利息 年3パーセント
遅延損害金 年14.8パーセント
返済期日 令和×年×月×日 - 2 保証債務
債権者 ○○ファイナンス株式会社
主債務者 住所 福山市△△町1-1
氏名 □□
保証契約日 令和○年○月○日
借入元本 300万円
利息 年3パーセント
遅延損害金 年14.8パーセント
返済期日 令和×年×月×日
4、遺言書の財産目録を作る場合の注意点
財産目録を作成する際に注意したい点について解説します。
-
(1)自筆証書遺言の財産目録は署名押印が必要
自筆証書遺言を作成する場合、財産目録の部分は自筆で作成する必要はありませんが、財産目録の用紙すべてに遺言者の署名押印が必要です。
自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、方式を誤ると遺言が無効になる可能性もあるので注意が必要です。 -
(2)すべての財産を特定できるように記載する
遺言書は遺言する方が亡くなった後で初めて遺族の目に触れることになるので、書面だけで正確に遺言の内容が伝わるように記載する必要があります。
財産目録も、登記簿や通帳、残高証明書などの資料を参照して、正確に特定事項を記載するようにします。
また、せっかく財産目録を作成しても、財産の漏れがあると相続税の申告や遺産分割のやり直しになることもあるので注意が必要です。 -
(3)貸金庫がある場合は財産目録に記載しておく
相続人にとって貸金庫の存在は気づきにくい場合もあります。貸金庫に現金や貴金属などを保管している場合は、財産目録にその旨を記載しておきましょう。
なお、貸金庫の契約者が亡くなった場合、貸金庫の開錠は相続人全員の同意と、金融機関によっては相続人全員の立ち会いを求められることもあるようです。
遠方に居住している相続人がいるような場合は、遺言で遺言執行者を指定し、貸金庫の開錠や内容物の取り出し、解約の権限を付与しておくことも選択肢となります。
お問い合わせください。
5、まとめ
財産目録は、遺言書の作成に取り組む際にまず作成したい資料といえます。相続手続の負担軽減や、ご自身の意向に沿った相続を実現するためにも、遺言書は大変有効です。また、ご自身のライフプランや遺言以外の相続対策を検討する際にも、財産目録を活用することができます。
ベリーベスト法律事務所 福山オフィスでは、財産目録や遺言書作成のサポートをはじめ、相続対策全般についてご相談を承っております。
当グループ所属の税理士とも提携しているので、税務に関するご相談も各種専門家と連携してスムーズな対応が可能です。安心して遺言書の作成をしたいとお考えの際には、お気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|