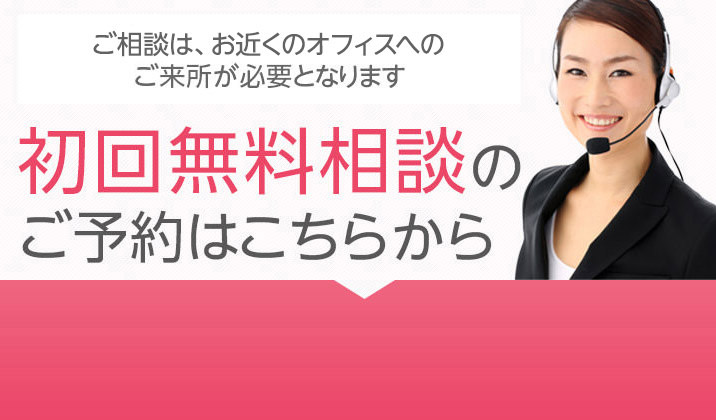ローンなしの持ち家に離婚後も妻が住むための法的課題と交渉術
- 離婚
- 離婚
- 持ち家
- 妻が住む
- ローンなし

持ち家を所有している夫婦が離婚する際は、離婚後にどちらが持ち家に住むのかを決めなければなりません。持ち家を売却するという方法もありますが、住宅ローンのない持ち家であれば、夫婦のどちらか一方が住むという選択をする方が多いと思います。
では、住宅ローンなしの持ち家に妻が住むにはどのような方法があるのでしょうか。持ち家は、夫名義になっていることも多いため妻が住むためには財産分与や名義変更などさまざまな手続きが必要になります。トラブルに発展する可能性もあるため、適切な対策を講じながら慎重に手続きを進めることが重要です。
今回は、ローンなしの持ち家に離婚後も妻が住むための法的課題と交渉術について、ベリーベスト法律事務所 福山オフィスの弁護士が解説します。


1、離婚後も妻が持ち家に住み続ける方法
ローンなしの持ち家がある場合、離婚後も妻が持ち家に住み続けるというのもひとつの選択肢になります。以下では、離婚後も妻が持ち家に住み続けることができる方法を紹介します。
-
(1)財産分与を受ける
夫婦が婚姻中に購入した持ち家であれば、基本的には共有財産にあたりますの、財産分与の対象になります。共有財産に含まれるかどうかは、財産の名義ではなく夫婦の協力関係より築いた財産であるかによって判断されるため、夫名義の持ち家であっても財産分与の対象にすることができます。
財産分与によって、持ち家をもらうことができれば離婚後も引き続き妻が住むことが可能です。 -
(2)買い取る
夫が親から相続した持ち家の場合や、親からの遺産で一括購入した持ち家である場合には、夫が単独で所有する財産(特有財産)にあたります。そのため、このような持ち家は財産分与の対象には含まれません。
特有財産に該当する夫名義の持ち家に妻が住むための方法としては、夫から持ち家を買い取る方法が考えられます。築年数の浅い持ち家だと評価額が高額になるため、妻の財産では買い取ることが難しいかもしれませんが、築年数の古い持ち家になるとほとんど価値がない状態になるため、妻の財産でも買い取りができる可能性があります。
持ち家の買い取りを希望する場合には、現在の持ち家の価値を把握する必要があるため、不動産会社に依頼して持ち家の査定をしてもらうとよいでしょう。 -
(3)賃貸借契約を結ぶ
夫名義の持ち家に妻が住む方法としては、夫と妻との間で賃貸借契約を締結するという方法もあります。
財産分与や持ち家の買い取りといった方法では、ある程度のまとまった金額の支払いが必要になるため、経済的に余裕がない状態ではそのような選択肢が取れない方もいると思います。しかし、賃貸借契約を締結する方法であれば、家賃を夫に支払うことで引き続き持ち家に住むことができるため、経済的な負担を最小限に抑えることができます。
離婚後、子どもの生活環境を変えたくないものの、経済的な余裕もないという場合には、夫と相談して賃貸借契約という形で持ち家に住むことを提案してみるとよいでしょう。
2、ローンのない持ち家の財産分与を受ける方法と注意点
持ち家を妻が財産分与で取得するにはどうすればいいのでしょうか。以下では、住宅ローンなしの持ち家に財産分与により妻が住む方法と注意点を説明します。
-
(1)財産分与の基礎知識
財産分与とは、婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産を離婚時に清算する制度です。
財産分与の対象となる財産には、現金、預貯金、不動産、有価証券、保険、退職金などがあり、夫婦どちらの名義であるかにかかわらず、夫婦の協力関係により維持・形成された財産であれば共有財産として財産分与の対象となります。
夫名義の持ち家であったとしても、婚姻期間中に住宅ローンを組んで購入したものであれば、財産分与の対象となる共有財産に該当するため、財産分与を求めることで持ち家に妻が住むことが可能になります。 -
(2)夫名義、共有名義の持ち家の名義変更手続きについて
持ち家の名義人が夫になっている場合、財産分与により持ち家を取得した妻は、夫から妻に名義変更を行わなければなりません。形式的には、夫から妻に財産が移転した形になりますが、もともと夫婦の共有財産であったものを分けただけであり、新たに財産を取得したわけではありませんので贈与税が課税されることはありません。
また、持ち家が共有名義の場合には、共有者間での持分割合を見直したうえで、名義変更を行うことが必要です。共有名義のままでは、持分割合が維持されるため、今後の財産トラブルを避けるためにも適切な手続きを進めることが推奨されます。
住宅ローンなしの持ち家であれば金融機関の承諾なども不要ですので、夫婦だけで不動産の名義変更を完結させることができます。 -
(3)不動産価値の半額を妻が支払えないときはどうすべきか
財産分与は、夫婦の貢献度に応じて共有財産を分けることになりますが、基本的には夫婦の貢献度は等しいと考えられています。そのため、財産分与の割合は、原則として2分の1となります。
たとえば、住宅ローンなしの持ち家の評価額が2000万円である場合において、妻が持ち家を取得する場合、2000万円分の財産を取得することになるため、その半分である1000万円を夫に支払わなければなりません。そのため、妻の資産状況によっては、夫に対して、不動産価値の半額を支払えない可能性もあります。
そのような場合は、その他の財産も含めて財産分与を考えてみるとよいでしょう。多くの夫婦は、不動産以外にも現金、預貯金、有価証券、保険、退職金などの共有財産を持っています。持ち家を妻が取得する代わりにその他の財産の中から不動産価値の半額を夫が取得するという方法であれば、2分の1ルールに従った財産分与を実現することができます。
また、お互いの合意があれば財産分与の割合を2分の1以外にすることも可能ですが、財産分与の割合が不自然に偏り、分与された財産が過大と判断される場合には、贈与とみなされて、贈与税が課税される可能性がありますので注意が必要です。
3、名義は変えずに住み続ける方法と注意点
金銭的な問題などで、夫名義の持ち家の名義を妻に変更することが難しいケースはどうすればいいのでしょうか。その場合は、名義は夫のままで、妻が住み続けるという方法をとることも可能です。
以下では、夫名義の持ち家に妻が住む場合において、名義を変えずに済み続ける方法とその際に注意点を説明します。
-
(1)必ず賃貸借契約か使用貸借契約を結ぶこと
夫名義の持ち家を財産分与や買い取る方法で妻が取得した場合には、所有者が変更になりますので持ち家の名義変更が必要になります。
しかし、夫から持ち家を「借りる」という方法であれば所有者は、依然として夫のままですので名義を変えずに住み続けることができます。このような方法をとる場合には、夫との間で賃貸借契約または使用貸借契約を締結するようにしましょう。
賃貸借契約とは、毎月賃料を支払って持ち家に住み続ける方法です。賃貸借契約の方法をとる場合、周辺の家賃相場などを参考にしながら、適正な賃料を定めるようにしてください。
使用貸借契約とは、賃料を支払わずに無償で持ち家に住み続ける方法です。賃料の負担がないという点では妻にとって有利といえますが、使用貸借契約は賃貸借契約よりも弱い権利とされています。そのため、無償で夫名義の持ち家に住ませてもらう場合は、夫からいつでも追い出されてしまうリスクがある点に注意が必要です。
どちらの方法をとるにしてもルールを明確にしておく必要があります。必ず書面により賃貸借契約または使用貸借契約を締結するようにしてください。 -
(2)児童扶養手当に影響が出る可能性がある点に注意
離婚後、子どもと一緒に生活する親に対しては、「児童扶養手当」が支給されます。夫名義の持ち家に離婚後も妻が住む場合には、児童扶養手当の金額に影響が出る可能性があるため注意が必要です。
児童扶養手当の所得制限限度額の算定にあたっては、扶養義務者の所得だけでなく、離婚した配偶者から支払われる養育費の8割相当額が加算されます。養育費には、養育費名目で支払われるお金だけではなく、子どもの養育と関係のある一切の費用が含まれます。夫名義の持ち家に妻が無償で済んでいる場合、夫から家賃相当額の援助を受けているとみなされるかもしれません。
そのため、具体的な状況によっては児童扶養手当の全部または一部の支払いがストップする可能性もあります。詳細については、お住まいの自治体または弁護士へ相談することをおすすめします。
4、離婚後も持ち家に住み続けるための交渉術
離婚後も妻が持ち家に住み続けるためにも、以下のポイントを押さえて交渉を進めていきましょう。
-
(1)感情的にならずに冷静に話し合いを進める
相手と交渉する際に感情的になってはいけません。感情的になって相手のことを批判すると、相手もこちらの要求に応じてくれなくなってしまうかもしれません。
そのため、交渉をするときは感情的にならず冷静に話し合いを進めるようにしてください。自分だけでは冷静な対応が難しいときは、弁護士に依頼するのがおすすめです。弁護士に依頼することで弁護士が代理人として交渉してくれますので、冷静な話し合いを進めることができます。 -
(2)条件に優先順位を付けてある程度の譲歩の姿勢を示す
離婚にあたっては相手に対してさまざまな要求があると思いますので、まずは希望条件について優先順位をつけるようにしてください。離婚後も持ち家に住むということが最優先だという場合には、その他の条件については相手との話し合いの中で譲歩の姿勢を示すことで相手もこちらの要求に応じてくれる可能性が高くなります。
離婚条件に優先順位をつける際には、適正な相場を把握する必要がありますので、まずは弁護士に相談してアドバイスしてもらうとよいでしょう。
-
(3)第三者を交えて話し合いを進める
離婚後も持ち家に住み続けるための交渉を行う際、夫婦間だけで話し合いを進めることが難しい場合があります。このような場合には、第三者を交えて話し合いを進めることが効果的です。
具体的には、家庭裁判所の調停手続を利用することが挙げられます。調停手続では、中立的な調停委員が夫婦間の意見調整をサポートし、公平な視点から解決策を提案してくれます。また、弁護士を代理人として立てることで、感情的な対立を避けながら、法的な根拠に基づいた交渉を行うことができます。
第三者を交えることで、冷静かつ効率的に交渉を進められる可能性が高まりますので、話し合いが行き詰まった場合には積極的に検討するとよいでしょう。
5、まとめ
離婚後、夫名義の持ち家に妻が住む方法には、財産分与、買い取り、賃貸借契約などがあります。ご自身の状況に応じて適切な方法を選択することで、離婚後も引き続き持ち家に住むことが可能になりますので、あきらめずに交渉を進めていきましょう。
離婚や財産分与の問題を解決するには専門家である弁護士のサポートが必要になりますので、離婚問題でお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 福山オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています