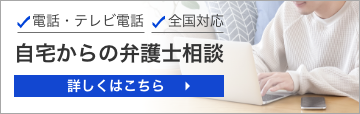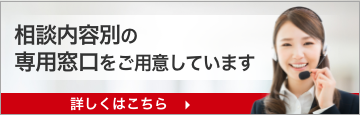労働条件の不利益変更|注意すべきことと適切な進め方
- 労働問題
- 労働条件
- 不利益変更

令和5年度に広島県内の総合労働相談コーナーに寄せられた労働に関する相談は3万3035件で、そのうち労働基準法等の違反の疑いがあるものは6030件でした。
賃金カットなどの労働条件の不利益変更をする際には、原則として労働者(従業員)の同意を得なければなりません。例外的に同意なき不利益変更が認められることもありますが、要件を満たしているかどうか慎重に検討すべきです。
本記事では労働条件の不利益変更について、要件・手続き・リスク・注意点などをベリーベスト法律事務所 福山オフィスの弁護士が解説します。
1、労働条件の不利益変更とは?
労働条件の不利益変更とは、文字通り、労働条件を労働者にとって不利益に変更することをいいます。
本章では、具体的な不利益変更の例、労働者の同意の必要性、例外的に労働者の同意がなくても、労働条件の不利益変更が認められるケースについて解説します。
-
(1)労働条件の不利益変更の具体例
労働条件の不利益変更に当たるものとしては、具体的に以下の例が挙げられます。
- 賃金の減額
- 定期昇給の廃止
- 基本給の額を据え置きつつ、固定残業代を含める(実質的な基本給の減額)
- 所定休日の減少
- 夏季休暇や年末年始休暇を、有給休暇扱いにする
- 所定労働時間の延長
- 無期雇用契約から有期雇用契約への転換
- 懲戒事由の追加、厳格化
-
(2)労働条件の不利益変更には、原則として労働者の同意が必要
労働条件の不利益変更は、原則として就業規則の変更によって行うことができません(労働契約法第9条本文)。したがって、労働条件の不利益変更を行う際には、原則として労働者の同意を得る必要があります。
なお、労働者にとって有利な労働条件の変更は、就業規則の変更によって行うことができると解されています(同法12条)。 -
(3)労働者の同意がなくても、労働条件の不利益変更が認められるケース
以下の①~③の要件をすべて満たす場合には、就業規則の変更によって、例外的に労働条件の不利益変更を行うことができます(労働契約法第9条但し書き、第10条)。
【例外的に労働条件の不利益変更が認められるための必要要件】
① 変更後の就業規則を労働者に周知すること
② 就業規則の変更が合理的であること
変更が合理的なものであるかは、以下の(1)~(5)の要素に照らして判断します。
(1)労働者の受ける不利益の程度
(2)労働条件の変更の必要性
(3)変更後の就業規則の内容の相当性
(4)労働組合等との交渉の状況
(5)その他の就業規則の変更に係る事情
③ 労働契約において「就業規則の変更があっても変更しない」と合意していた労働条件でないこと(就業規則で定める基準に達しない労働条件を除く)
上記①~③の要件をすべて満たす場合は、労働者の同意を得ることなく労働条件の不利益変更をすることができます。
2、労働条件の不利益変更をする際の手続き
労働条件の不利益変更をする際には、以下の流れで手続きを行いましょう。
-
(1)労働者と話し合い、同意をお願いする
労働者とのトラブルを避けるため、労働条件の不利益変更は労使の合意に基づいて行うことが望ましいです。
まずは労働者と話し合い、労働条件の不利益変更に対して同意してもらえるようお願いしましょう。経営不振など、不利益変更が必要である理由を丁寧に説明すれば、労働者の同意を得られる可能性があります。 -
(2)同意なき不利益変更の可否を検討する
労働者の同意を得られないときは、就業規則の変更によって労働条件の不利益変更ができるかどうかを検討しましょう。
特に、合理性の要件(1章(3)「例外的に労働条件の不利益変更が認められる要件」 )を満たしているかどうかが重要なポイントです。
労働者にとって大幅に不利益になる場合や、経営状態が健全である場合などには、同意なき労働条件の不利益変更は認められにくいです。
安易な労働条件の不利益変更は行わず、労働者の同意を得ずに労働条件の不利益変更をしようとする際には、弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。 -
(3)就業規則を変更する
同意なき不利益変更の要件を満たすと判断した場合には、不利益変更を盛り込んだ就業規則の変更を決定しましょう。
就業規則の変更は、取締役会決議や取締役の過半数の同意などによって行います。
常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を変更するに当たり、過半数労働組合または労働者の過半数代表者の意見を聞かなければなりません(労働基準法第90条第1項)。
就業規則の変更に関する労働者側の意見は、意見書にまとめて提出してもらいましょう。 -
(4)変更後の就業規則の内容を労働者に周知させる
変更後の就業規則の内容は、労働者に対して周知させなければなりません。周知を怠ると、労働条件の不利益変更の効力が生じないのでご注意ください(労働契約法7条本文)。
変更後の就業規則の周知は、以下のいずれかの方法によって行う必要があります(労働基準法施行規則第52条の2)。- ① 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付ける
- ② 書面を労働者に交付する
- ③ 使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルまたは電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する
-
(5)変更後の就業規則を労働基準監督署に届け出る
常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を変更した場合には、その内容を労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法第89条)。
就業規則の変更の届出に当たっては、労働者の意見書(前述)を添付する必要があります(同法第90条第2項)。労働者の意見書や就業規則の変更届は、定型の様式がなく、適宜の様式によって作成することができます。
書式については、厚生労働省のウェブサイト「主要様式ダウンロードコーナー」(労働基準法等関係主要様式) に様式例が掲載されているので、参考にしてください。
お問い合わせください。
3、労働条件の不利益変更に伴うリスクと注意点
労働条件の不利益変更は、適法に行うことができる場合でも、企業にとっては大きなリスクを伴います。
弁護士のアドバイスを受けつつ、本当に労働条件の不利益変更を行うべきかどうか慎重に検討することが重要です。
-
(1)労働条件の不利益変更に伴うリスク
労働条件の不利益変更をすると、労働者の仕事に対するモチベーションが低下する可能性が高いです。また、待遇が悪い企業というイメージが広まると、人材採用にも悪影響が生じてしまうでしょう。
さらに、労働者が労働条件の不利益変更の無効を主張してくることも想定されます。深刻な労使トラブルに発展すると、企業にとっては対応に多大なコストを要する上に、他の労働者への悪影響も懸念されます。
労働条件の不利益変更によって人件費をカットできても、それ以上のデメリットが生じるおそれがある点に十分ご注意ください。 -
(2)労働条件の不利益変更をする際の注意点
労働条件の不利益変更をする際には、労働者に対して丁寧に説明を尽くすことが大切です。労働条件の不利益変更が真にやむを得ないと納得してもらえば、労使トラブルのリスクを抑えることができます。
労働条件の不利益変更に当たっては、労働者の同意を得ることが望ましいですが、同意を強要してはいけません。使用者によって強要された労働者の同意は無効です。また、労働者側が反発して、深刻な労使トラブルに発展するおそれもあります。
労働条件の不利益変更を行うとしても、弁護士のアドバイスを受けながら慎重に検討と手続きを進めましょう。
4、労働条件の不利益変更を検討する際には、弁護士に相談を
労働条件の不利益変更は、労使トラブルの大きなリスクをはらんでいます。労働者に納得してもらえるように説明を尽くしつつ、法律の根拠に基づいて手続きを進めるためには、弁護士によるサポートが欠かせません。
ベリーベスト法律事務所には、労働問題の解決実績が豊富な弁護士が在籍しています。労使トラブルのリスクを最小限に抑えるため、どのような対応を行うべきかについて具体的にアドバイスいたします。
経営不振などにより、労働条件の不利益変更を検討している企業は、お早めに当事務所の弁護士へご相談ください。
5、まとめ
労働条件の不利益変更を行う際には、労働者の同意を得ることが望ましいです。同意が得られない場合は、労働契約法の要件に従って、同意なき労働条件の不利益変更ができるかどうかを検討しましょう。
労働条件の不利益変更には大きなリスクを伴うため、弁護士に相談しながら検討することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所は、労務管理に関する企業のご相談を随時受け付けております。経営不振などによって労働条件の不利益変更をしたいと考えている企業は、まずはベリーベスト法律事務所 福山オフィスへご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています