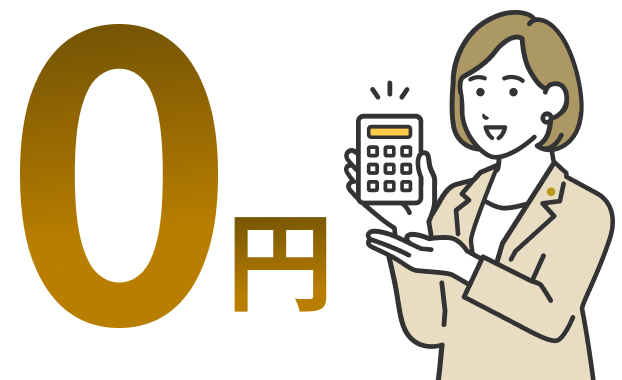債権の相続方法は? 時効や相続できない債権の種類、注意点を解説
- 遺産を受け取る方
- 債権
- 相続

福山市の一部を管轄する福山税務署では、令和4年の1年間で約1500名が相続税の申告を行いました。
相続税は、相続財産の価額に応じて課税の有無や税額が決定されるため、相続が発生した場合は、相続財産を正確に把握することが重要です。相続の対象になるのは、亡くなった方が所有していた財産ですが、そのなかでも「債権」と呼ばれる権利は、やや理解しづらい面があります。
債権とは、人と人との間に生じる権利のことで、種類が多様であることに加え、相続の対象外となるものや、性質上分割できないものも存在します。そこで、今回のコラムでは、債権を相続した場合の相続手続きや注意点について、ベリーベスト法律事務所 福山オフィスの弁護士が解説します。
出典:「令和4年 直接税(相続税)」(国税庁)


1、債権の相続方法は?
債権とはどのような権利なのか、債権を相続する際の基本的な流れについて解説します。
-
(1)債権とはどのような権利か
債権は、特定の人(債権者)が他の特定の人(債務者)に対して、一定の行為を求める権利です。相続することが多い債権は、金銭の支払いを求める金銭債権で、主に以下のようなものがあります。
- 貸金債権:お金を貸していた場合の請求権
- 賃料債権:不動産などを賃貸していた場合の賃料の請求権
- 代金債権:商品やサービスを提供した対価としての代金の請求権
- 損害賠償請求権:交通事故や契約不履行などによる損害賠償を請求する権利
- 預貯金債権:銀行などに対する預貯金の払い戻しを請求する権利
金銭債権以外にも、購入した物の引き渡しを求める権利や、賃貸借契約に基づいて物件を使用収益する(貸し出して利益を得る)権利など、さまざまな債権が存在します。被相続人(亡くなった方)の債権は、原則として相続人に引き継がれますが、相続人が複数いる場合、債権の種類や性質によって相続方法が異なります。 -
(2)債権の種類と相続手続き
債権は、可分債権と不可分債権に分類され、複数の相続人がいる場合は、この区別により相続手続きに大きく影響します。
なお、遺言書がある場合は、基本的に遺言の内容に従って遺産を分配することになりますが、ここでは遺言書がない場合の相続手続きについて解説します。① 可分債権
可分債権とは、分割して履行してもらえる債権のことです。多くの金銭債権が可分債権に該当し、上記の金銭債権のうち、預貯金債権以外は可分債権です。
額面が確定した金銭債権は、たとえば300万円の債権を150万円ずつ弁済してもらうというように、額面で分割できることから、可分債権とされています。
可分債権は、相続開始(被相続人が亡くなったタイミング)と同時に相続人の相続分に応じて自動的に分割され、各相続人に帰属します。つまり、可分債権は、特別な手続きなしで債権を取得することができます。
なお、預貯金債権など一部の金銭債権は不可分債権として扱われますが、その理由は後述します。
② 不可分債権
不可分債権はその性質上、分割して履行することができない債権のことです。不動産など特定物の引き渡し請求権や、請負契約により成果物を納品してもらう権利などが典型的な例です。
不可分債権は、可分債権のように自動的に分割されることはありません。法律が示す相続人(法定相続人)全員で話し合って遺産分割を行い、誰が不可分債権を取得するのか決めることになります。不可分債権の取得については、相続人全員の合意が必要ですが、合意がなされなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割審判を行うことになります。相続人同士の対立が大きい場合、遺産分割は長期化するケースもあるでしょう。
不可分債権は、相続人同士の話し合いによる遺産分割が必要で、可分債権は自動的に分割されるため、遺産分割が不要、といった違いがあります。 -
(3)預貯金、株式、個人向け国債、投資信託
金銭債権の中でも、現金化が比較的容易な預貯金や株式、個人向け国債、投資信託は、いずれも不可分債権として扱われて、不動産のほか、現金や貴金属などの動産とともに遺産分割の対象となります。
かつて、預貯金は可分債権と考えられており、相続開始直後でも払い戻しを受けられる扱いが一般的でした。
しかし、平成28年12月に最高裁が従来の判断を変更し、預貯金も不可分債権として遺産分割の対象になると判断しました。そこから、相続の手続きは大きく変わることになりました。
こうした背景には、預貯金に対し、現金は遺産分割の対象となるため、その不整合の是正のための判断だったと考えられます。また、遺産分割の対象を拡大して、実質的に公平な相続を実現するのが望ましいという判断が働いたとも考えられています。
2、相続の対象にならない債権
相続が発生すると、被相続人の財産に属する一切の権利義務を相続人が承継することになりますが、「一身専属権」といわれるものは、相続の対象外とされています。一身専属権とは、特定の人のみが行使できる権利のことを意味します。
以下、相続できない主な債権について解説します。
-
(1)扶養請求権・年金受給権・生活保護受給権
扶養請求権、年金受給権、生活保護受給権は、一定の身分関係や特定人の資格に基づいて発生するため、一身専属権として、相続の対象外となります。
扶養請求権は、夫婦や親子、兄弟姉妹間で、互いの生活維持のために扶養を求める権利です。
特定の身分関係が前提となるため、相続できません。
また、年金受給権や生活保護受給権も、一定の受給資格を満たした人のみが受けられる権利であり、一身専属権として相続の対象外です。 -
(2)離婚に伴う財産分与請求権
財産分与請求権は、離婚後の元配偶者が行使できる一身専属的な権利です。
ただし、財産分与請求権には、夫婦共有財産(預金や不動産など、婚姻期間に夫婦で築いた財産)の清算、慰謝料、離婚後の扶養料(経済的に豊かな方が、そうでない方に支払う、生活扶助のための金銭)の3つの要素があり、具体的な請求権の内容により判断する必要があります。
夫婦共有財産の清算と慰謝料は、一般的な財産権としての性格が強いため、相続の対象になると考えられています。一方、離婚後の扶養料は、一身専属的な性質が強く、相続の対象外になるという考え方が主流です。
なお、財産分与について具体的な合意が成立した後に一方の配偶者が亡くなった場合、これらの要素は通常の債権として、相続の対象になります。 -
(3)ゴルフ会員権
ゴルフ会員権は、ゴルフクラブの構成員としての性質があるものや、優先プレー権などの特典が得られるものなどの形態がありますが、規約により譲渡や相続を制限しているケースもあります。
規約で、会員の死亡により資格喪失と定められている場合は、一身専属的権利として相続の対象にはなりませんが、そのような規約がなければ相続することができます。また、解約により預託金が返還される場合、預託金返還請求権は相続の対象となります。
3、債権を相続する場合の注意点
債権を相続した場合に、理解しておきたいポイントを解説します。
-
(1)可分債権の相続と法定相続分
可分債権は、先述のとおり、相続の開始から特別な手続きをしなくとも取得できますが、相続人が複数いる場合は、それぞれが法定相続分を取得することになります。法定相続分とは、法律で定められた相続人それぞれの相続割合のことで、相続割合は相続人の構成により決まります。
たとえば、相続人が被相続人の配偶者と子2人のケースを考えましょう。法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1なので、その割合に応じて相続した債権を行使することが可能です。
なお、本来可分債権は自動で分割されますが、相続人全員の合意があれば、不可分債権のように遺産分割の対象にすることができます。 -
(2)預貯金の相続と仮払い制度
預貯金は遺産分割が成立するまで払い戻しを受けられませんが、そうなると、相続人が相続税の納税資金などに困ることもあるでしょう。そのため、令和元年7月から2つの仮払い制度が整備されています。
ひとつは、法定相続分の3分の1に相当する金額(最大150万円)まで、金融機関での手続きにより、単独で払い戻しを受けられる制度です。
もうひとつは、家庭裁判所での仮払い申請に関する制度です。もともと、家庭裁判所に申し立てることで、ほかの相続人の利益を侵害しない範囲で仮払いが認められていましたが、その要件が緩和されて利用しやすくなっています。
もっとも、これらの仮払いを受けた場合は、その金額は遺産分割の際に考慮されることになります。 -
(3)債権には消滅時効がある
債権には消滅時効があり、一定期間権利を行使しないと権利が消滅することがあります。債権の一般的な時効期間は5年とされていますが、その成立時期や種類によって異なることがあり、正確な時効期間を把握するには法的知識が必要です。
また、時効期間の起算点は、原則として権利を行使することができるとき、つまり行使できると知ったときから進行します。被相続人が亡くなった時点ですでに進行していた時効は、そのまま相続人に引き継がれます。したがって、債権を相続した際には、まず時効の状況を確認しましょう。
なお、法律の定める事実があった場合は、必要な手続きを踏むことで、時効の更新や時効までの猶予を得られる場合もあります。 -
(4)債権は回収できるとは限らない
債権を相続しても、必ずしもその債権を回収できるとは限りません。債務者に支払い能力がない場合のほか、債務者から債権の存在を否定されたり、支払う金額について同意を得られなかったりするリスクも考えておく必要があります。
したがって、債権を相続した際には、弁護士など法律の専門家のアドバイスを受けて、その債権の回収可能性を慎重に評価することをおすすめします。
4、遺産相続で悩んだら弁護士に相談を
相続手続きを進める際は、弁護士に相談しましょう。
たとえば、弁護士は遺産分割の円滑な進行をサポートできます。預貯金債権があれば、遺産分割が発生するため、実態として多くの相続で遺産分割は避けられません。複数の相続人がいれば、話し合いが難航することもあるでしょう。その際、弁護士であれば、法律に基づいた解決策を提案することができます。また、裁判を通じた解決が必要な場合は、裁判手続きを行うことも可能です。
さらに、公平な遺産分割が実現するために、生前贈与などの遺産分割で考慮すべき事項についてのアドバイスや、遺産分割協議書など法的効力のある書類作成もできます。
相続した債権の債務者など、関係者との交渉も、弁護士がサポート可能です。債務者に対する法的根拠のある請求や、債権の時効の管理など、専門的な法律知識が必要な場面で適切なアドバイスを受けられます。さらに、弁護士は債務者との交渉のほか、交渉が決裂して裁判になった際のすべての手続きについて、代理人となれる点も大きなメリットです。
相続手続きを円滑に進めるためには、問題が大きくなる前に対処することが重要です。そのため、なるべく早めに弁護士に相談することをおすすめします。
お問い合わせください。
5、まとめ
債権の相続は、その種類や状況に応じて適切な手続きが必要になります。可分債権と不可分債権の区別による相続手続きの違い、公平な遺産分割の実現、時効の管理など、法的知識が必要な場面も少なからずあります。
債権の回収まで見据えた上で、相続手続きを円滑に進めるためには、早い段階から弁護士などの専門家のサポートを受けることが有効です。
ベリーベスト法律事務所では、遺産相続に関するご相談を随時受け付けております。債権の相続についてのお悩みの際は、ベリーベスト法律事務所 福山オフィスへご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています