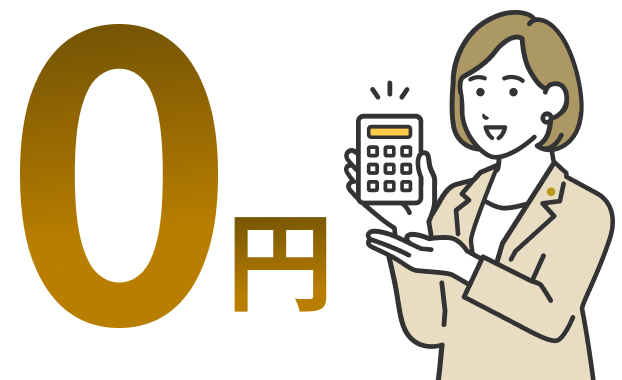身内が孤独死したら相続放棄するべき? 遺産相続の流れと注意点
- 相続放棄・限定承認
- 相続放棄
- 孤独死

総務省の情報通信白書(2018年版)によると、65歳以上の単独世帯率は2040年にはおよそ40%に達すると予測されています。こうした単独世帯の増加にともない、社会的リスクとして注視されるのが「孤独死」の問題です。
現状では「自分には無縁だ」と思われる方もいるかもしれません。しかし、ある日疎遠になっていた身内が孤独死をして相続問題が発生するというケースもあります。
疎遠になっていた分、相続財産をまったく把握できておらず、相続放棄をすべきか悩むこともあるでしょう。ベリーベスト法律事務所 福山オフィスの弁護士が解説します。


1、孤独死とは
まずは孤独死の定義と現状について解説していきます。
-
(1)孤独死の定義
法律上は孤独死の定義が定められていません。そのためさまざまな定義があり得るところですが、一般的には「誰にも看取られず1人で死ぬこと」と定義されています。
孤独死となった方は社会的に孤立し、経済的にも困窮しているケースが少なくありません。そのため、借金や賃貸の未払いがあった場合は、遺品をたどって遠縁の親族に連絡がくることがあります。
孤独死された方の相続が発生した際には、預金や不動産のようなプラスの財産だけではなく、借金や損害賠償責任といったマイナスの財産があることを想定し、しっかり調査することが大切です。 -
(2)孤独死の現状
2022年に発表された「第7回孤独死現状レポート(一般社団法人日本少額短期保険協会)」によると、孤独死の対象になり得る「単独世帯」の数が、全世帯数のおよそ4割にもおよんでいることがわかりました。
孤独死の平均年齢は約62歳であり、平均寿命よりもおよそ20歳も若い段階で亡くなっています。また、「現役世代」と定義されている20〜60歳で亡くなった方が4割に及ぶことから、決して高齢者だけの問題ではないこともわかってきたのです。さらに、男女比では男性の方が女性の約4倍多く孤独死しています。孤独死のうち、死因の1位が病死、2位が不明、3位が自殺であることは男女共通しています。
孤独死で発見に時間がかかると、ご遺体が腐敗して居室の原状回復にコストがかかったり、事故物件として入居者が決まらないという損害が発生したりするなど、相続人のリスクが高まる可能性もあります。
「孤独死」とは決して高齢者だけの問題ではなく、身近に起こりうる問題なのです。
2、孤独死した身内の遺産は相続放棄するべきか
身内が孤独死した場合、相続財産がわからない不安から相続放棄を考える方は少なくありません。
そこで、相続放棄のメリットデメリットや、身内が孤独死した場合に相続放棄すべき具体的なケースを解説していきます。
-
(1)相続放棄とは?
相続には3つの方法があり、相続人はそれぞれ相続方法を選ぶことができます。
1つ目はプラス財産もマイナス財産も全て相続する「単純承認」です。この方法がもっとも多く選択されています。
2つ目はプラス財産の範囲内でマイナスの財産を相続する「限定承認」です。
そして3つ目がプラスの財産もマイナスの財産も全て相続しない方法で、これを「相続放棄」といいます。相続放棄ができる期間は限られており、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し出てなければなりません。 -
(2)相続放棄のメリットとデメリット
相続放棄は、メリットとデメリットを理解した上で、状況にあわせて選択することが大切です。相続放棄のメリットとデメリットは以下の通りです。
相続放棄の主なメリット
- マイナスの財産を引き継がなくて済む
- 遺産相続のトラブルに巻き込まれない
- 特定の相続人に財産を全て承継させることができる
相続放棄の主なデメリット
- プラスの財産を引き継ぐことができない
- 相続放棄をすると撤回できない(取り消しができる場合はある)
- 相続放棄をしない他の相続人がマイナスの財産を負担しなければならない
-
(3)相続放棄すべき2つのケース
身内が孤独死した場合に相続放棄をすべき、代表的なケースを2つご紹介します。
① 被相続人の借金が多いケース
被相続人の相続財産を調査して、プラス財産よりも借金が多い場合は相続放棄を検討した方が良いでしょう。
② 被相続人が賃借人で、居室の原状回復費用が高額になるケース
前述のとおり、孤独死された被相続人が賃借人だった場合、ご遺体の発見の遅れに伴い賃貸物件の原状回復費用が高額になることがあります。
相続をすると家主への損害賠償責任も受け継ぐため、プラス財産よりも原状回復費用が高い場合は相続放棄を検討しましょう。
3、遺産相続の流れと注意点
相続放棄が「相続開始を知った時から3か月以内」という手続きの期限があるように、相続をする場合にも手続きの期限があります。
相続発生から相続をするまでの流れと注意点についても知っておきましょう。
-
(1)遺産相続の流れ
遺産相続は以下の流れで行います。
- ① 遺言書の有無の確認
- ② 相続人の調査・確定
- ③ 相続財産の調査
- ④ 相続方法の選択
- ⑤ 遺産分割協議
- ⑥ 相続手続き
- ⑦ 相続税の申告・納付
以下、ひとつずつ確認していきましょう。
① 遺言書の有無の確認
まずは被相続人が遺言書を作成しているかどうか確認しましょう。遺言書には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があります。
公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」の有無は、公証役場で検索できます。また「秘密証言遺言」も同様の遺言検索システムで探すことができます。
被相続人が自ら作成する「自筆証書遺言」の有無は、「自筆証書遺言保管制度」を被相続人が利用している場合、「遺言書保管事実証明書」の交付を「遺言書保管所」に請求することで確認することが可能です。
「自筆証書遺言保管制度」を利用せず自宅で保管しているケースもあるため、「遺言書保管所」で見つからなかった場合は被相続人の遺品や家の中を確認するようにしましょう。
② 相続人の調査・確定
遺言書がない場合、遺産分割協議を行うためにも誰が法定相続人に当たるのか調査・確定する必要があります。遺言書がある場合は原則その内容にしたがって手続きを進めるため相続人の調査は必要ありません。
③ 相続財産の調査
被相続人の財産の内容を調査・確定しましょう。相続財産は預貯金や不動産、貴金属や車などの動産といったプラスの財産に加えて借金などのマイナスの財産も全て調査します。
④ 相続方法の選択
「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つから相続人がそれぞれ選択しましょう。
⑤ 遺産分割協議
遺言書がない場合、遺産をどのように分けるかを法定相続人が話し合って決めます。この話し合いが「遺産分割協議」です。相続人全員が合意したら「遺産分割協議書」を作成しましょう。
⑥ 相続手続き
遺言書や遺産分割協議書にしたがって、遺産の名義変更や不動産の相続登記などの手続きを行います。
⑦ 相続税の申告・納付
相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は原則として相続税の申告・納付が必要です。
以上が遺産相続のおおまかな流れです。 -
(2)遺産相続の注意点
遺産相続をする際に気をつけなければならないことを3点解説します。
① 家で自筆証書遺言を見つけたらその場で開けてはいけない
「自筆証書遺言」を見つけたらその場で開けて内容を確認したくなることでしょう。しかし決して開けてはいけません。
なぜなら、自筆証書遺言は偽造・変造を防止するために家庭裁判所で「検認」を請求しなければならないからです。「検認」は相続人立ち会いのもと、家庭裁判所で遺言書を開封・確認する手続きで、検認をする前に開封すると5万円以下の過料を科せられるおそれがあります。
そのため、自筆証書遺言を見つけてもその場で開封せず、すぐに家庭裁判所に検認の請求をしましょう。
② 遺産分割協議は相続人全員が参加しなければならない
遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があります。なぜなら、相続人が1人でも足りない状況で合意した遺産分割協議は無効になってしまうからです。そのためにも、相続人の漏れがないように相続人の調査・確定は慎重に行いましょう。
③ 相続手続きには期限がある
遺産相続の中には期限のある手続きが複数あります。
主な期限のある手続きは以下のとおりです。- 相続放棄(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)
- 限定承認(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)
- 相続税の申告、納付(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)
- 遺留分侵害額請求(相続と遺留分侵害を知ってから1年以内)
- 相続した不動産の相続登記(相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内)
「相続した不動産の相続登記」は所有者不明の土地問題の解決のために、2024年4月1日から義務化されることになりました。
なお、遺産相続手続きの期限の起点は、原則として「相続人が相続開始を知った時」です。相続人は相続開始、つまり被相続人の死亡を知った時から期限以内に各種手続きを行うように注意しましょう。
4、相続放棄をするかしないか判断に迷った時の対処法
相続をするか相続放棄をするか悩んでいるうちに相続放棄の可能な時期を逃してしまったということがないように、迷ったら弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は相続人に代わって「相続人調査」を行えます。また、遺産分割協議や相続放棄の判断のためにも重要である「相続財産調査」も可能です。被相続人の預貯金や不動産、株式の有無や借金の有無など調査内容は多岐にわたりますが、調査が長引くと相続放棄の期限に間に合わないこともあるでしょう。弁護士に依頼することで、早く正確な調査を行い遺産分割協議の開催や相続放棄の判断をすることができます。
また相続放棄をするかどうかでお悩みの際にも、弁護士から状況に応じたアドバイスを受けることが可能です。遺産相続開始からやらなければならない手続きは多々あり、期限が短いものもあります。漏れのない手続きをするためにも、まずは弁護士にご相談ください。
お問い合わせください。
5、まとめ
身内が孤独死をすると、どう行動をすればいいのかわからず不安に感じる方は多いでしょう。しかし手をこまねいている間に、相続放棄の申請期限である3か月が過ぎてしまうおそれがあります。
とくに孤独死の場合は被相続人が賃借人の場合、原状回復費用が高額になることがあるため、相続をするのか相続放棄をするのか相続財産調査を厳密に行った上で判断することが重要です。
孤独死をした身内の財産を相続放棄すべきか、相続手続きを何から始めたらいいのかわからず不安など、お悩みがありましたら、まずはぜひベリーベスト法律事務所 福山オフィスの弁護士までご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています